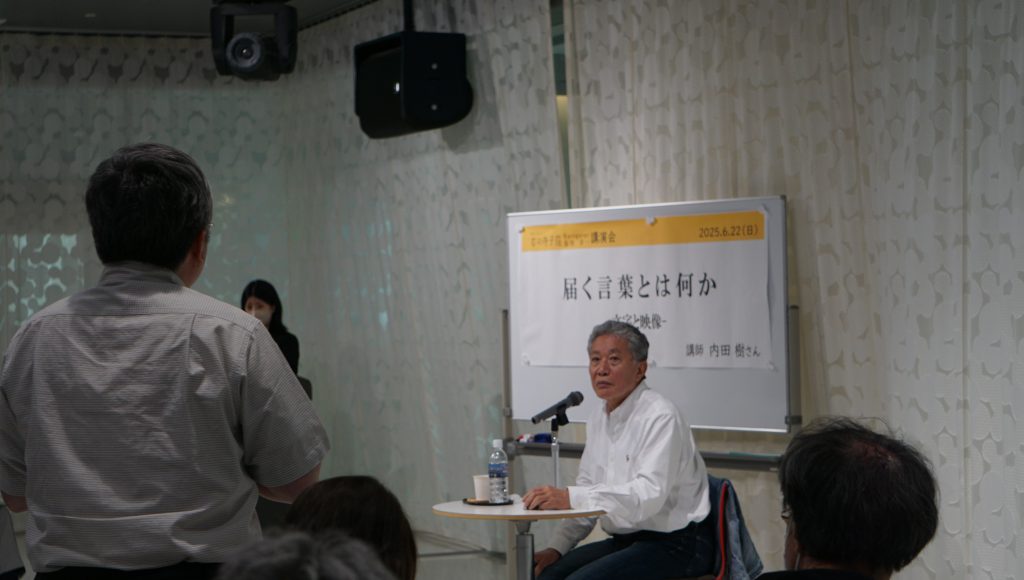6月22日(日)、凱風館館長で神戸女学院大学名誉教授の内田樹さんをお招きして講演会を開催しました。
信濃毎日新聞のコラムや執筆された本のエピソードを交えながら、届く言葉とは何か、ときにユーモアも含めながらお話いただきました。
講演概要
最初に、「この辺りは信濃毎日新聞のエリアなのですね」と信毎でのコラム執筆の話題に。
一回で話が終わらなかったときに本当はダメだけれど、“続きは来週”という手をつかわせてもらい最大4回まで続けた。担当の方が優しくてなにを書いても怒られない、信毎に書くのが一番気楽だと話されました。
テーマについて話していきますが、テーマ通りにならないかもしれない。寛容にお願いしたい。と前置きをしてから本題へ。
最近、東大の工学系大学院が授業を英語でおこなうことが賛否両論話題になった、高等教育が英語でおこなわれることの弊害について。
母語で高等教育を受けさせないのは植民地化の基本だった。母語で教育ができないとイノベーションが起きない。
母語はネオロジズムがつくれる。母語から生まれた新語は初めて聞いた言葉でも意味がすべての話者に伝わる。母語のアーカイブは沈黙の言語。
さらに、話題は以前執筆した修業論や教育論についての著書にまつわるエピソードへ。
“修業”という概念はアメリカ人には理解できない。それはどうしてなのか、英語には“修業”という意味の言葉が存在しないからで、プラクティスやエクササイズという言葉はあるがどれも意味が異なる。“修業”は相対的な優劣を示す指標がない。そのことが理解し難いようだと話されました。
次に理解できない、共感できない他者へ言葉を届ける難しさについてへ。
武道で自分が自分であることは“居着き“といって、我執(がしゅう)という言葉もある。
アイデンティティという言葉をあえて訳すのなら我執、アイデンティティポリティクスは我執政治ともいえる、自分の属すグループのためだけに戦う我執政治では理解も共感もできない人を排除しようとする。
自分の属するグループの為だけに戦うアイデンティティポリディクスは辞めようとずっと提唱していて、共感集団の中だけに届く言葉でなく、共感集団を超えて届かせるにはどうしたら良いのか、最近自分のなかで課題として考えている。
最後に、自分は共感性のない人間だけれど、知識・情報の上に構築されたコミュニケーションをしている。共感や同一性ではなく記号レベルのコミュニケーションが精密にできるとどんなタイプの他者とも共生できる。これからの日本人は共感集団のなかだけで伝わる言葉だけでなく、他者にも届く言葉を考え獲得しよう。
他者に届く言葉が語れるような成熟した市民になりたいですね、と講演会を締めくくられました。
日時
2025年6月22日(日) 14:00~16:00
場所
塩尻市市民交流センター(えんぱーく) 多目的ホール
講師
内田 樹(うちだ たつる)さん
1950年東京都生まれ。神戸女学院大学名誉教授、神戸市で武道と哲学研究のための学塾「凱風館」を主宰、合気道凱風館師範(合気道七段)。東京大学文学部仏文科卒業。東京都立大学人文科学研究科博士課程中退。専門は20世紀フランス文学・哲学、武道論、教育論など。主著に『ためらいの倫理学』、『レヴィナスと愛の現象学』、『寝ながら学べる構造主義』、『先生はえらい』『武道的思考』など。
『私家版・ユダヤ文化論』で第六回小林秀雄賞、『日本辺境論』で2010年度新書大賞、第三回伊丹十三賞を受賞。
近著に『勇気論』、『図書館にはひとがいないほうがいい』『動乱期を生きる』(山崎雅弘との共著)など。