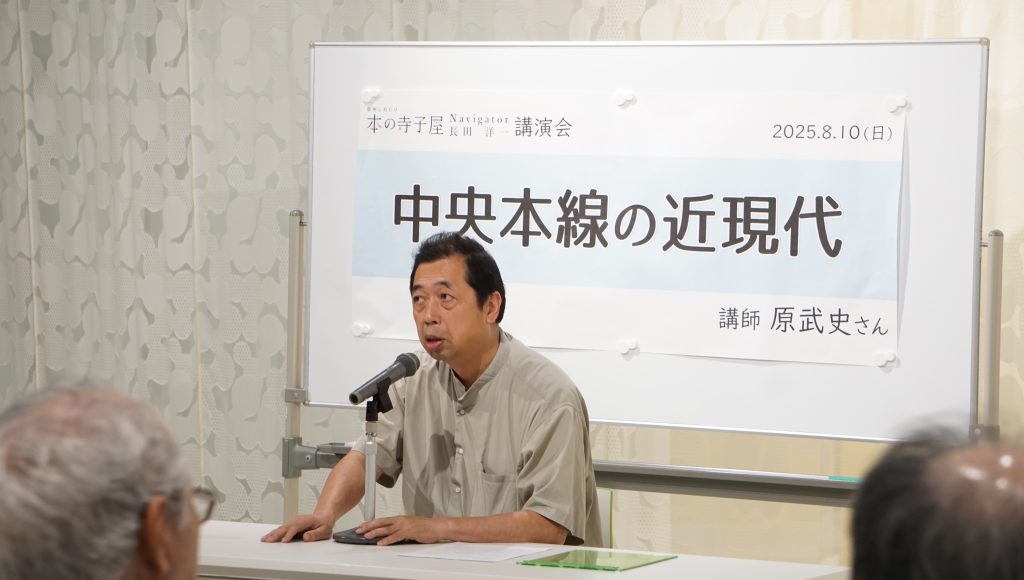8/10(日)、明治学院大学名誉教授で政治学者の原武史さんより「中央本線の近現代」と題し、中央本線の沿線で生まれた政治風土や歴史についてのお話をお聞きしました。
講演概要
はじめに中央本線との原さん個人の関りについて、幼少時代から遡りお話していただきました。原さんが5,6歳の時、新宿駅から松本駅までの駅名を全て暗記されていたそうです。家族旅行ではよく急行を利用していたので、特急に対して強い憧れを抱いていました。「子供料金が最後の年は、特急で名古屋-松本間、松本-武蔵小金井間を一人旅した」といったエピソードをお話していただきました。
次に中央本線の名称について教えていただきました。正式名称は、東京-名古屋間が中央本線で、俗称として東京-高尾間が中央線(東京近郊区間)、新宿-塩尻間を中央東線、塩尻-名古屋間が中央西線と呼ばれているそうです。正式名称の中央本線よりも、俗称である中央東線、中央西線の方が定着しているそうです。
1872年10月14日に新橋-横浜間に鉄道を開業されました。明治政府が東京-京都間に街道に代わって鉄道を開通するときに東海道経由と中山道経由の案があったそうです。結局白紙撤回になった理由は、地形の問題や費用がかさむことから東海道経由になりました。
お茶の水-八王子間は、私鉄の甲武鉄道として開業されました。東中野-立川間は一直線で、日本で2番目に長い直線区間です。甲州街道の宿場が廃れるから反対されたからという説と、一直線上に作るのが一番合理的だった説があります。直線だというのが中央線の政治風土を考える上で重要ではないかと思っているとおっしゃっていました。
1906年の鉄道国有法で甲武鉄道が買収され東京-塩尻-名古屋間が中央本線になりました。1914年東京駅が開業、1919年に万丸の内駅舎の一、二番線から中央線が発車しています。万世橋-東京間が開通し、中央本線の起点が東京駅になりました。
長野県では上京する際のターミナルが、北信は上野、南信は新宿と別れていました。同じ長野県民でもイメージする東京のイメージが違い、上野につながっている北信は野暮ったさ、新宿につながっている松本は開明的なイメージがありました。昭和初期は電化されている区間は大都市だけでしたが、例外があり、長いトンネルがあると電化されました。都会でしかさずかれない近代化の波が中央本線は早かったとおっしゃっていました。
昭和初期に東京-立川間が電化され、朝夕ラッシュ時に2分間隔、その他の時間帯も4分間隔で運転。中央線のダイアは非常に充実していました。1930年には電車区間が浅川まで伸びて、今の中央線の基本ができました。しかし、この時点で日本の鉄道で一番進んでいたのは関西。例えば阪急は、この当時から大阪-神戸間を25分で走らせていました。当時京王線の新宿-東八王子間は70分かかりました。
昭和初期になると中央線沿線の宅地開発が進み、政治家や作家やリベラル派の知識人が競って移り住みました。共産党系の知識人は西武沿線に多かったそうです。
つづいて戦後の中央線と政治運動についてお話していただきました。1950年戦後の中央本線を考えるうえで大きな転機は朝鮮戦争がきっかけになりました。立川には戦前は陸軍の飛行場があったが、敗戦後は米軍の基地になりました。中央線沿線に住んでいた作家・佐多稲子が「往来列車の音が朝鮮戦争の後変わった」と言ったそうです。頻繁に立川へ燃料を運ぶ貨物列車の往来が激しくなりました。それだけでなく、立川に米軍兵が集まり、風紀が乱れるようになりました。国立にも影響があり、いかがわしいホテルが乱立。それに対して立ち上がったのは、国立に住んでいるお母さん方でした。子どもの教育に影響があるとされ、住民運動が活発に行われました。最終的に東京都から文教地区の指定を勝ち取りました。住民運動の歴史の中にも輝かしい歴史としてよく知られています。普段から議員に政治をまかせるのではなく、普段から住民がしっかり監視をしましょうという運動がここで活発になっていきました。これを推し進めたのは無党派の女性たちです。これは中央線の政治風土を考えるうえで、重要な動きでした。
1954年にはアメリカがビキニ環礁で水爆実験を行いました。原水禁運動の発祥の地も中央線の荻窪です。当時公民館の館長だった安井郁が中心となって、原水禁運動を起こします。国立の浄化運動と共通しているのは、反米的な政治風土です。中央線沿線の人達は、たえず貨物列車の存在を通してアメリカを意識せざるを得ませんでした。水爆実験をしたことで、非常に大きな反発が生まれました。そういった運動がピークに達したのが1960年の安保闘争で、戦後最大の市民運動でした。
中央線沿線では無党派市民の動きが活発でした。一つの例が豊田の多摩平団地です。この時小林富、鶴見俊輔、高畠通利など主婦や学者が集まって党派的でなく、誰でも気軽に参加できる会として作ったのが「多摩平声なき声の会」。これが安保闘争の中心に発展していきました。無党派市民を主体とする運動だという点においては、国立の浄化運動、荻窪の原石運動と共通しています。つまり、中央線の政治風土を特徴づけているのは、特定の党派に偏らない、幅広い市民による運動が、荻窪や国立などいろんなところから繰り出されてきました。
1966年に新宿駅が池袋駅を抜いて乗車人員が日本一になりました。中央線だけでなく、この頃になると、京王線、小田急線など新宿に乗り入れる私鉄の沿線が開発されました。小田急沿線では軒並み大団地ができました。それによって新宿が通勤客で膨れ上がりました。
1960年代後半にベトナム反戦運動が起こりました。そのきっかけとなったのは1967年8月新宿駅構内で起こった「米軍燃料輸送列車事故」。日々新宿を通る中央線で、このような列車が往来している事実が明るみに出てしまい、もともと中央線沿線にあった反米的な政治風土に火をつけました。
1968年10月21日に「新宿騒乱」という大きな事件がありました。新左翼が主導したとされますが、やじ馬も加わって、大変な騒乱でした。そこになぜ普通のサラリーマンがやじ馬で加わったのでしょうか。中央線沿線にもともとあった反米的な政治感情を抜きにしては考えられません。新宿駅は「政治の季節」の一大拠点でした。2011年以降の反原発運動も高円寺から起こりました。
最後に信州の出版社についてお話していただきました。塩尻市立図書館は、筑摩書房と非常に関係が深い。これ以外、岩波書店、みすず書房のような硬派な出版社の創業者も南信出身。戦後、岩波書店が「世界」を創刊し、戦後の民主主義運動をリードしました。筑摩書房は「展望」を創刊、非常に論壇的なものを載せていました。つまり戦後の論壇をリードしていくような出版社がこの辺りからでてきたことは、中央線沿線の政治風土と密接につながっているような気がしてなりませんとおっしゃっていました。
「鉄道の沿線から戦後史を見ていくと、中央線に関してはそれが一層よくあてはまる。政治学者は空間、沿線、地域に対して、もっと目を向けてほしい」と講演を締めくくられました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
原武史さん、ご参加いただいた皆さん、ありがとうございました。
日時
2025年8月10日(日) 14:00~16:00
場所
塩尻市市民交流センター(えんぱーく) 多目的ホール
講師
原 武史(はら たけし)さん
1962年東京都生まれ。東京大学大学院博士課程中退。明治学院大学名誉教授。放送大学客員教授。日中文化交流協会理事。高千穂あまてらす鉄道総合研究所理事。講談社本田靖春ノンフィクション賞選考委員。著書に『「民都」大阪対「帝都」東京』(サントリー学芸賞)、『大正天皇』(毎日出版文化賞)、『滝山コミューン1974』(講談社ノンフィクション賞)、『昭和天皇』(司馬遼太郎賞)、『歴史のダイヤグラム』、『日吉アカデミア1976』 、 『日本政治思想史』など。2024年、日本政治法律学会現代政治学会賞受賞。